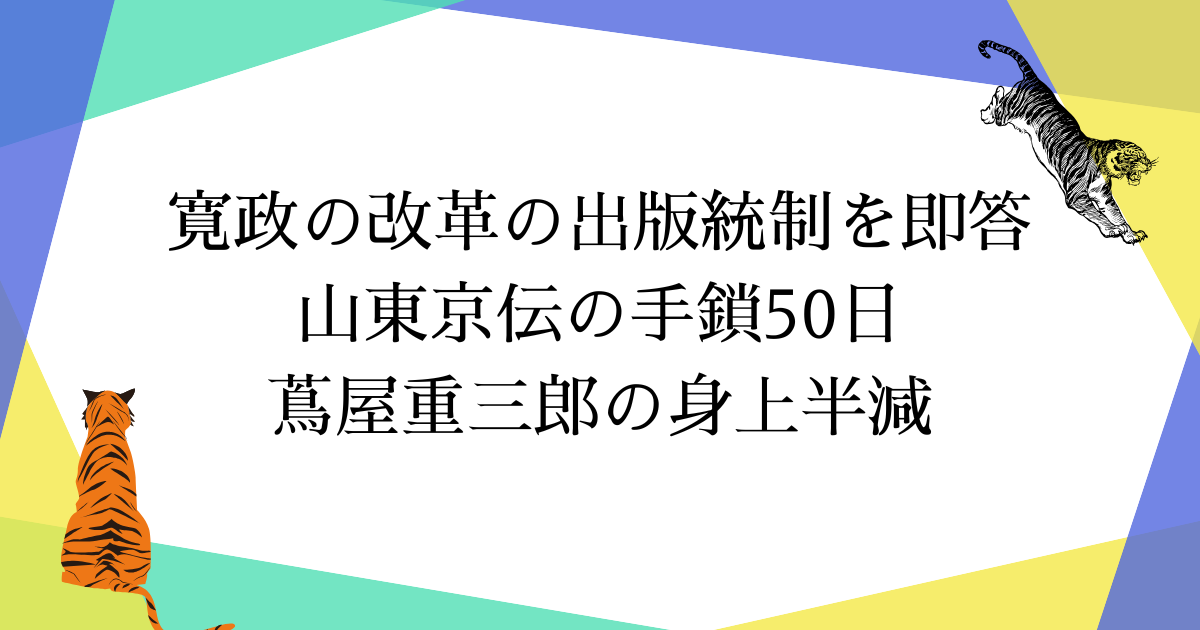寛政の改革における出版統制とは、洒落本や黄表紙など、風紀を乱すとされた出版物が取り締まりの対象となり、作者や版元に厳しい処分が科された政策です。
この記事では、山東京伝と蔦屋重三郎が受けた処罰の具体的な内容と、その背景を分かりやすく解説します。
結論
結論(即答)
寛政の改革による出版統制では、洒落本などが標的となり、山東京伝は手鎖50日、蔦屋重三郎は身上半減の処分を受けました。
この背景には、地本問屋による事前検閲「行事改」の義務化があります。
寛政の改革を主導した松平定信の生涯や性格、田沼意次との対立理由については、こちらで詳しく解説しています。
山東京伝の処分(手鎖50日)
寛政三年(1791年)、洒落本3作が咎められ、山東京伝は手鎖50日の刑に処せられた。
【出典】蔦重ワールド
「手鎖(てじょう)50日」とは、50日間、自宅で手錠をはめられた状態で謹慎するという、作家活動を完全に封じられる厳しい処罰でした。
蔦屋重三郎の処分(身上半減)
寛政三年(1791年)、蔦屋重三郎は身上半減(家財半減)の処罰を受けたが、年収半減とする解釈もある。
【出典】Nippon.com
「身上半減」は、一般的に財産の半分を没収されるという、版元として再起不能になりかねないほどの重い処罰でした。
出版統制の中身(対象と手続き)
遊里を舞台にした風刺・滑稽の読物や社会風刺を含む作品群が標的となった。
【出典】Waraku Web
寛政2年、地本問屋の事前検閲「行事改」が義務化され、『類集撰要』10月27日付に地本問屋20軒の連署(蔦屋重三郎)が確認できる。
【出典】Nippon.com
行事改は月番行事による仲間内吟味で、のちに名主改(改掛名主)へ主体が移るなど制度は変遷した。
影響と余波(作品・市場への波及)
京伝が手鎖50日、蔦重が身上半減の罰を受けると、出版界は自粛ムードへ転じた。
【出典】Wedge
多くの作家や版元が活動を自粛する一方、蔦屋重三郎は喜多川歌麿の美人画や東洲斎写楽の役者絵といった、新たなジャンルの開拓へと向かいました。弾圧が、結果的に新たな文化を生み出すきっかけになったとも言えるでしょう。
寛政の改革の出版統制 まとめ
寛政の改革における出版統制は、江戸の自由な創作活動に大きな打撃を与えました。
しかし、蔦屋重三郎のような版元は、その逆境の中でも新たな才能を見出し、江戸の文化をより豊かなものへと発展させていったのです。
FAQ(よくある質問)
- なぜ洒落本が狙われた?
-
遊里を舞台にした風俗・会話などの写実性が風紀を乱すとされ、出版統制の主要対象となりました。
- 山東京伝の処罰は?
-
寛政3年(1791年)に洒落本で手鎖50日の処分を受けました。
- 蔦屋重三郎の「身上半減」とは?
-
蔦屋重三郎の「身上半減」とは?