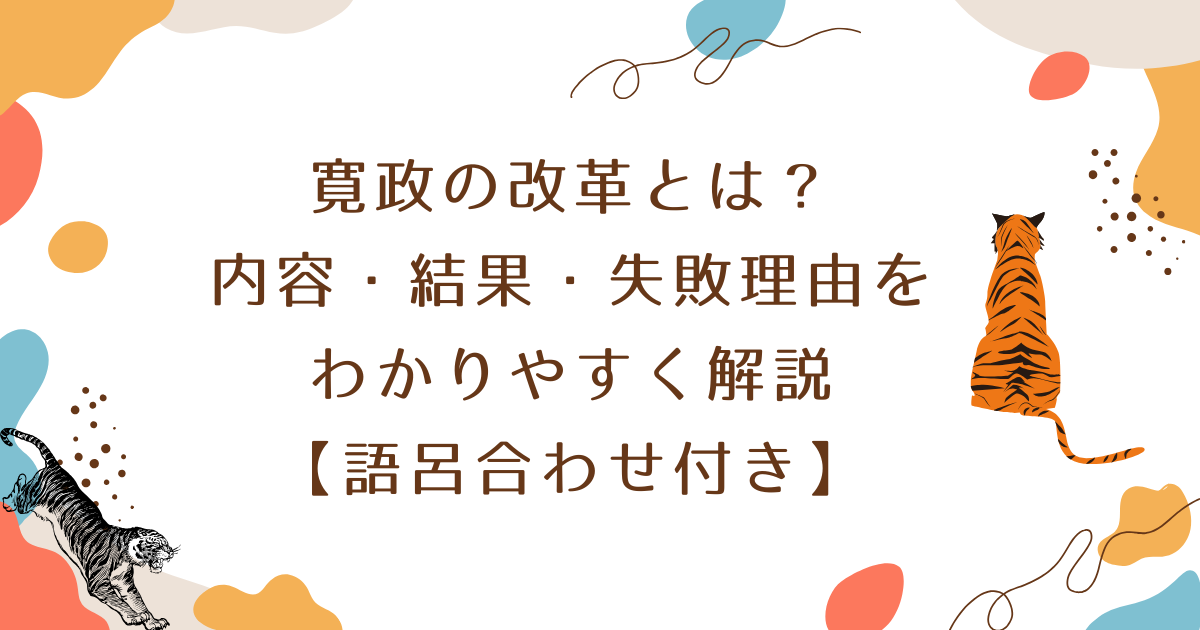江戸時代の三大改革の一つ「寛政の改革」。教科書では必ず出てくる重要な歴史用語ですが、「いつ」「誰が」「何をしたのか」を正確に答えられますか?
寛政の改革とは、1787年(天明7年)から1793年(寛政5年)の6年間、老中・松平定信が主導した江戸幕府の政治改革です。
この記事では、改革の具体的な内容10項目、成功した点と失敗した理由、享保・天保の改革との違いまで、大手メディアと歴史辞典の一次情報のみでわかりやすく解説します。
【この記事の信頼性について】
本記事は以下の方針で執筆しています
- 一次情報のみ使用:Wikipedia、日本国史大辞典、nippon.com、Serai.jp、白河市公式HPなど信頼できる情報源のみを使用
- 出典を完全記載:すべての引用に日付とメディア名を記載し、検証可能な状態を維持
- 推測は明記:歴史的評価については諸説を併記
- 中高生にもわかりやすく:専門用語には必ず解説を付記
結論:寛政の改革とは松平定信が行った6年間の幕政改革
寛政の改革とは、1787年(天明7年)から1793年(寛政5年)の6年間、老中・松平定信が主導した江戸幕府の政治改革です。
3つのポイント
- 期間: 1787-1793年(6年間)
- 人物: 老中・松平定信(徳川吉宗の孫)
- 目的: 幕府財政の建て直し、農村復興、社会秩序の回復
出典: Wikipedia「寛政の改革」
年号の覚え方【語呂合わせ4選】
中学・高校の試験対策に便利な語呂合わせを紹介します。
① 非難はないか、寛政の改革(定番)
ひなん(1787)はないか、寛政の改革
出典: nihonshi-goro.com(2019年2月7日)
② 粋な花咲く寛政の改革(イメージ型)
いきな(1787)花咲く、寛政の改革
出典: nihonshi-goro.com(2019年2月7日)
③ 批難半端ない、寛政の改革(インパクト型)
ひなん(17)はんぱ(8)ない(7)、寛政の改革
出典: real-juku.jp(2025年3月3日)
④ 里にもどって粋な花咲く松平(政策連想型)
里にもどって(旧里帰農令)いきな(1787)花咲く松平
出典: real-juku.jp(2025年3月3日)
いつ・誰が・なぜ始めた?寛政の改革の基本情報
いつ:1787年〜1793年(寛政年間)
松平定信が老中に就任した1787年(天明7年)6月から、老中を辞任する1793年(寛政5年)7月までの約6年間です。
寛政年間(1789-1801年)の前半を中心とした改革だったため、「寛政の改革」と呼ばれます。
出典: Wikipedia「寛政の改革」(2004年7月12日初版)
誰が:老中・松平定信(徳川吉宗の孫)
松平定信(まつだいらさだのぶ、1758-1829年)は、8代将軍・徳川吉宗の孫にあたる人物です。
田安家から白河藩(現在の福島県白河市)の藩主となり、天明の大飢饉(1782-1787年)を見事に乗り切った手腕を買われ、1787年6月、わずか30歳で老中首座(老中の最上位)に就任しました。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
- 出典: Wikipedia「松平定信」(2004年5月10日初版)
- 出典: JBpress(2025年4月23日)
なぜ:田沼時代の失政と天明の大飢饉
寛政の改革が始まった背景には、前任の老中・田沼意次の重商主義政策の破綻と、天明の大飢饉による社会の混乱がありました。
田沼時代(1767-1786年)の問題点
- 賄賂と縁故による人事が横行
- 商人優遇政策で農村が疲弊
- 幕府の権威が失墜
天明の大飢饉(1782-1787年)の被害
- 全国で約92万人が餓死
- 農村が荒廃し、江戸に農民が流入
- 江戸で打ちこわしが多発
出典: JapanKnowledge「寛政の改革」(2025年9月3日)
定信は「田沼時代の政策を一掃し、緊縮財政と風紀の取り締まりによって、幕政を安定させよう」としたのです。
出典: Serai.jp「松平定信の生涯」(2025年1月31日)
寛政の改革の内容【10の主要政策】
① 棄捐令(きえんれい):旗本・御家人の借金帳消し
内容: 旗本・御家人が札差(金融業者)に負っていた借金のうち、6年以上前のものを全て帳消しにし、それ以降の借金も返済を大幅に猶予しました。
目的: 幕臣の経済的救済を図る
結果: 一時的に旗本・御家人は救済されたものの、札差が貸し出しを渋るようになり、かえって困窮する結果となりました。
出典: HugKum(2021年3月28日)
② 旧里帰農令(きゅうりきのうれい):農民を農村に戻す
内容: 江戸に出稼ぎに来ていた農民に旅費や農具代を支給し、農村に帰って農業を続けるよう促しました。
目的: 農業人口の回復、農村の復興
結果: 強制力がなかったため、ほとんどの農民が従わず、失敗に終わりました。
出典: JapanKnowledge「寛政の改革」(2025年9月3日)
③ 囲米の制(かこいまいのせい):飢饉に備えた米の備蓄
内容: 各藩に対し、石高1万石につき50石の米を備蓄するよう命じました。
目的: 飢饉対策、農村の安定
結果: 天保の大飢饉(1833-1839年)の際、一定の効果を発揮しました。
出典: JapanKnowledge「寛政の改革」(2025年9月3日)
④ 七分積金(しちぶつみきん):町内の災害対策基金
内容: 江戸の各町内の必要経費(町入用)を節約し、その7割を積み立てさせ、災害時の救済資金としました。
目的: 都市の災害対策、貧民救済
結果: 一定の成果を上げ、江戸の治安維持に貢献しました。
出典: 白河市公式HP「寛政の改革」(2023年12月31日)
⑤ 石川島人足寄場(いしかわじまにんそくよせば):無宿者の職業訓練施設
内容: 江戸の石川島(現在の中央区)に、無宿者(ホームレス)を収容し、職業訓練を行う施設を設置しました。
目的: 江戸の治安維持、無宿者の更生
結果: 一定の効果を上げ、江戸の治安改善に貢献しました。
出典: Serai.jp「松平定信の生涯」(2025年1月31日)
⑥ 異学の禁(いがくのきん):朱子学以外の学問を禁止
内容: 幕府の教育機関である湯島聖堂で、朱子学以外の学問(陽明学、古学など)を教えることを禁止しました。
目的: 幕府の思想統制、儒教道徳の徹底
結果: 学問の自由が奪われ、文化人や知識層の反発を招きました。
出典: Wikipedia「寛政の改革」(2004年7月12日初版)
⑦ 出版統制:風俗を乱す出版物の取り締まり
内容: 洒落本・黄表紙など風俗を乱すとされた出版物を取り締まり、作家や版元に厳しい処分が科されました。
目的: 風紀の取り締まり、幕府批判の抑制
結果: 華やかな江戸文化が衰退し、庶民の楽しみが奪われました。
出典: Nippon.com「寛政の改革と出版統制」(2025年9月2日)
関連記事:出版統制】
出版統制の詳細(山東京伝への手鎖50日、蔦屋重三郎への身上半減、行事改による事前検閲の仕組み)については、こちらで詳しく解説しています。
また、「身上半減」という処罰についてはこちらもご覧ください。
⑧ 倹約令(けんやくれい):贅沢禁止令
内容: 武士・町人を問わず、衣服・食事・住居など生活全般にわたり、極端な質素倹約を強制しました。
目的: 幕府支出の抑制、社会風俗の粛正
結果: あまりに厳しすぎたため、庶民や武士の強い反発を招きました。
出典: Serai.jp「松平定信の生涯」(2025年1月31日)
⑨ 大奥の抑制
内容: 無駄遣いの温床だった大奥(将軍の奥方たちの居住区)にも倹約を求めました。
結果: 浪費に慣れ切った奥女中の反感を買っただけで、効果はありませんでした。
出典: HugKum(2021年3月28日)
⑩ 公金貸付政策
内容: 豪農層に対し、年利1割前後で公金を貸し付け、その利子を荒地の復旧や農業人口の増加に活用させました。
目的: 農村復興、本百姓体制の再建
結果: 豪農層の存在を前提とした政策で、一定の成果を上げました。
出典: JapanKnowledge「寛政の改革」(2025年9月3日)
寛政の改革の結果【成功と失敗】
成功した点
① 幕府財政の一時的な黒字化
緊縮財政により、幕府の赤字を一時的に黒字に転じさせることに成功しました。
出典: Serai.jp「松平定信の生涯」(2025年1月31日)
② 農村の一定の復興
公金貸付政策や囲米の制により、天明の大飢饉で荒廃した農村を一定程度復興させました。
出典: JapanKnowledge「寛政の改革」(2025年9月3日)
③ 社会秩序の一時的な回復
石川島人足寄場や七分積金により、江戸の治安が改善しました。
出典: 白河市公式HP「寛政の改革」(2023年12月31日)
④ 幕府の権威回復
田沼時代に失墜した幕府の公儀性(公正な政治)を一時的に回復させました。
出典: Wikipedia「寛政の改革」(2004年7月12日初版)
失敗した理由(なぜ失敗したか)
① 極端な倹約令への反発
「倹約を徹底させる政策は、上層階級にはある程度の効果をもたらしたものの、庶民の間では大きな不満を呼びました。町人や農民にとって娯楽や贅沢は、生活の張り合いでもありました。それを一方的に制限する形になったことで、かえって生活の苦しさや不安が増してしまいます」
出典: HistoryNavi「寛政の改革とは?」(2025年5月13日)
「白河の清きに魚も棲みかねて もとの濁りの田沼恋しき」という狂歌が流行したほど、田沼時代の自由な風潮を懐かしむ人が多かったのです。
出典: HugKum(2021年3月28日)
② 出版統制による文化の衰退
厳しい出版統制により、華やかな江戸文化の自由な発展が阻害され、文化人や知識層を敵に回しました。
出典: HistoryNavi「寛政の改革とは?」(2025年5月13日)
③ 松平定信の失脚(1793年7月)
将軍・徳川家斉や側近、大名、大奥など、あらゆる方面からの反発により、定信はわずか6年で老中を辞任。改革は挫折しました。
「あまりに厳しい緊縮政治の結果、武士や庶民の不満が高まっていたことも理由にある」
出典: Wikipedia「寛政の改革」(2004年7月12日初版)
定信の失脚の詳細は下記の記事で解説しています。
④ 根本的な問題の未解決
田沼時代に促された藩の自立化を止めることはできず、幕府の権威低下という根本的な問題は解決できませんでした。
出典: Wikipedia「寛政の改革」(2004年7月12日初版)
歴史家の評価
「寛政の改革は江戸幕府の崩壊を50年ほど引き延ばした」
出典: 歴史学者・三上参次(Wikipedia「寛政の改革」より引用)
改革により時間を稼いだものの、幕末の危機を回避することはできなかった、という評価です。
享保の改革・天保の改革との比較
江戸時代の「三大改革」を比較してみましょう。
| 改革名 | 時期 | 人物 | 主要政策 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 享保の改革 | 1716-1745年 | 8代将軍・徳川吉宗 | 新田開発、公事方御定書、目安箱 | 成功(約30年継続) |
| 寛政の改革 | 1787-1793年 | 老中・松平定信 | 倹約令、異学の禁、出版統制 | 一時的成功(6年で挫折) |
| 天保の改革 | 1841-1843年 | 老中・水野忠邦 | 株仲間解散、人返し令、上知令 | 失敗(2年で挫折) |
享保の改革との最大の違い
享保の改革(徳川吉宗)は新田開発など生産力向上を重視したのに対し、寛政の改革は倹約と統制を重視した点が異なります。
吉宗は「増やす」政策、定信は「減らす」政策だったため、享保は成功し、寛政は失敗したとも言えます。
出典: hiroseki.sakura.ne.jp「江戸時代の三大改革」(2000年12月31日)
寛政の改革とは?まとめ
寛政の改革は、1787-1793年に老中・松平定信が行った江戸幕府の政治改革です。
- 期間: 1787-1793年(6年間)
- 人物: 松平定信(徳川吉宗の孫、30歳で老中首座)
- 内容: 棄捐令・旧里帰農令・囲米の制・七分積金・石川島人足寄場・異学の禁・出版統制・倹約令など10の政策
- 結果: 一時的な財政黒字化に成功も、極端な倹約令への反発により6年で挫折
極端な倹約と出版統制により、庶民・文化人・大名から強い反発を招き、松平定信は老中を辞任。改革は短期間で終わりましたが、歴史家・三上参次は「江戸幕府の崩壊を50年延ばした」と評価しています。
享保の改革(徳川吉宗)が「増やす」政策で成功したのに対し、寛政の改革は「減らす」政策で失敗した、という対比が興味深いですね。
寛政の改革や江戸時代の文化についてもっと知りたい方は、こちらもあわせてどうぞ。
FAQ(よくある質問)
寛政の改革はいつ行われましたか?
1787年(天明7年)から1793年(寛政5年)の6年間です。語呂合わせは「いやな(1787)改革、松平定信」です。
寛政の改革を行ったのは誰ですか?
老中・松平定信です。8代将軍・徳川吉宗の孫にあたり、1787年にわずか30歳で老中首座に就任しました。
寛政の改革の内容は何ですか?
棄捐令、旧里帰農令、囲米の制、七分積金、石川島人足寄場、異学の禁、出版統制、倹約令など10の主要政策があります。
寛政の改革は成功しましたか?
幕府財政の黒字化など一時的には成功しましたが、極端な倹約令への反発により、松平定信はわずか6年で老中を辞任しました。歴史家・三上参次は「江戸幕府の崩壊を50年延ばした」と評価しています。
享保の改革との違いは?
享保の改革(徳川吉宗)は新田開発など生産力向上を重視しましたが、寛政の改革は倹約と統制を重視した点が異なります。そのため、享保は約30年継続して成功しましたが、寛政は6年で挫折しました。
なぜ「白河の清きに魚も棲みかねて もとの濁りの田沼恋しき」という狂歌が流行したのですか?
松平定信の倹約令があまりに厳しすぎて、庶民の楽しみが奪われたため、「清すぎる(厳しすぎる)定信の政治より、多少濁っていても自由だった田沼時代の方がよかった」という皮肉を込めた狂歌が流行しました。
参考・出典
本記事の執筆にあたり、以下の信頼できる情報源を参照しました。
歴史辞典・百科事典:
- Wikipedia「寛政の改革」(2004年7月12日初版)
- Wikipedia「松平定信」(2004年5月10日初版)
- JapanKnowledge「寛政の改革」(2025年9月3日)
大手メディア:
- Nippon.com「寛政の改革と出版統制」(2025年9月2日)
- Serai.jp「松平定信の生涯」(2025年1月31日)
- JBpress「松平定信の寛政の改革」(2025年4月23日)
地方自治体公式サイト:
- 白河市公式HP「寛政の改革」(2023年12月31日)
教育・学習サイト:
- HugKum(小学館)「寛政の改革について知ろう」(2021年3月28日)
- HistoryNavi「寛政の改革とは?」(2025年5月13日)
語呂合わせ参考サイト:
- nihonshi-goro.com「寛政の改革の覚え方」(2019年2月7日)
- real-juku.jp「寛政の改革の語呂合わせ」(2025年3月3日)
その他:
- hiroseki.sakura.ne.jp「江戸時代の三大改革」(2000年12月31日)