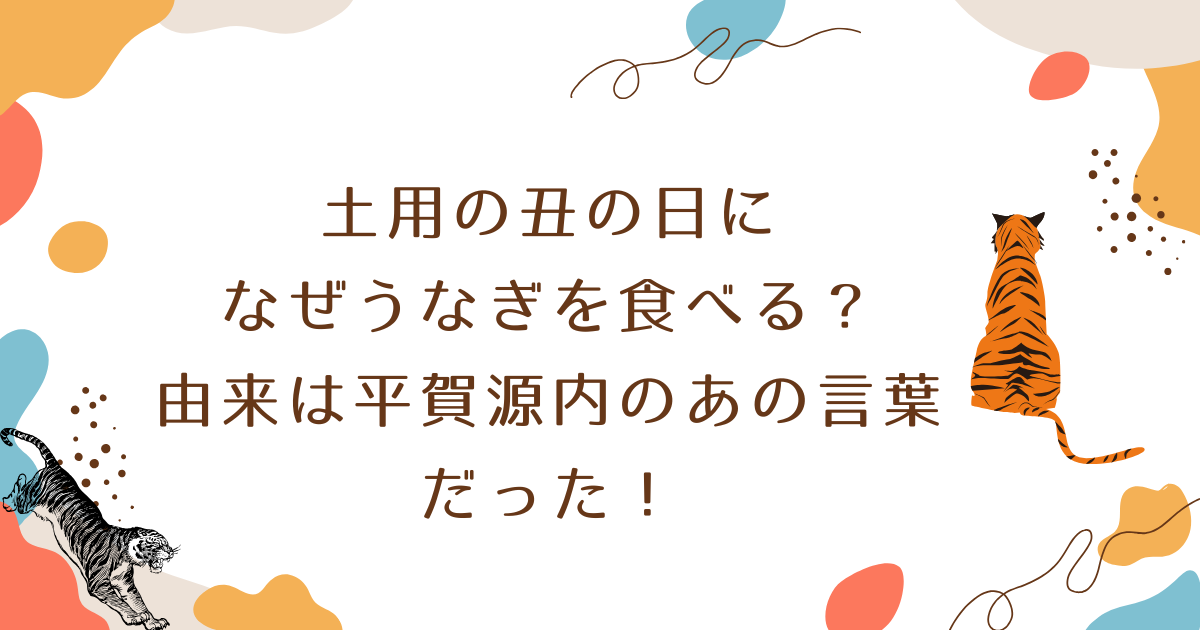夏の訪れを告げる、「土用の丑の日」。今年も、スーパーや飲食店の店先は、香ばしい匂いを漂わせる「うなぎ」で賑わいます。
しかし、ふと思ったことはありませんか?
「そもそも、なぜ私たちはこの日に、うなぎを食べるのだろう?」と。
実はその習慣、うなぎの旬が冬であるにもかかわらず、江戸時代の”ある天才”が仕掛けた、壮大なマーケティング戦略だったのです。
この記事では、そんな「土用の丑の日」の最大の謎から、現代の新しい楽しみ方まで、そのすべてを、どこよりも分かりやすく、そして面白く解き明かしていきます。
この記事で分かること
- なぜうなぎを食べる? すべての始まりとなった平賀源内の知られざる物語
- 2025年はいつ? 「土用の丑の日」の本当の意味と、該当日の一覧
- うなぎ以外は何を食べる? 話題の代替品や、「う」のつく食べ物まとめ
- してはいけないことって? 知って得する、古くからのユニークな風習
この記事を読み終える頃には、あなたも「土用の丑の日」博士になっているはずです。さあ、日本の夏の食文化を巡る、面白い旅に出かけましょう。
あわせて読みたい
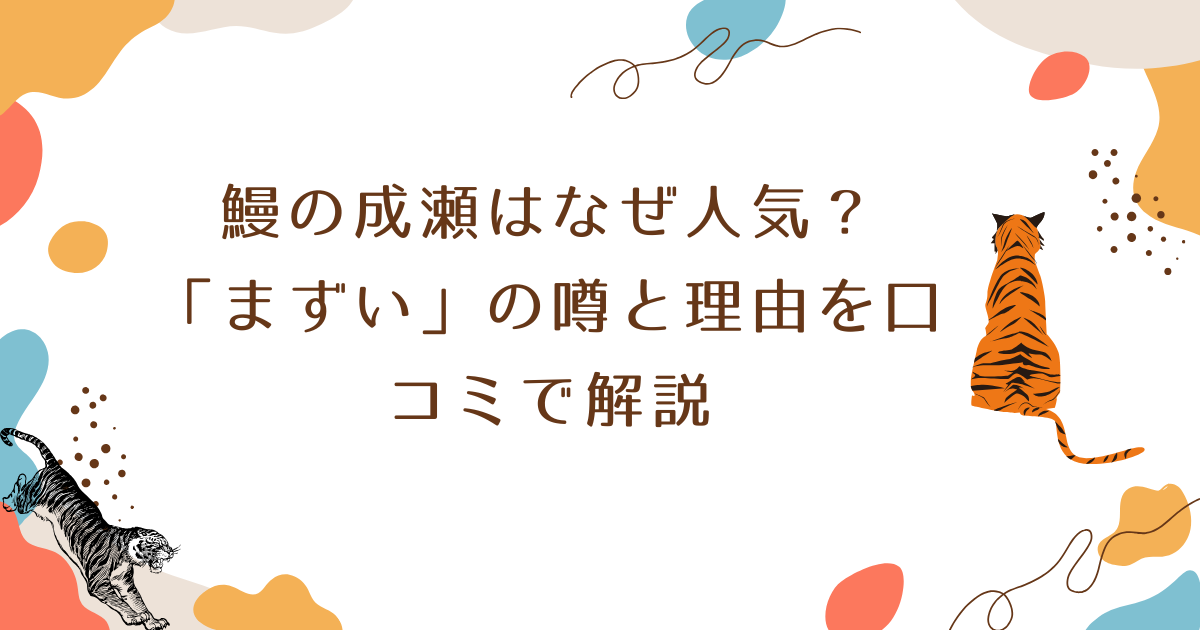
土用の丑の日にうなぎを食べる由来は、平賀源内のあの言葉
「土用の丑の日に、うなぎを食べる」。
今や、日本の夏の常識とも言えるこの習慣ですが、その由来を辿ると、一人の天才的な人物に行き着きます。
彼の名は、平賀源内(ひらが げんない)。
江戸時代に活躍した、医者であり、発明家であり、そして、現代の私たちを動かす言葉を生み出した、天才マーケターでした。
しかし、そんな彼の輝かしい功績の裏で、その最期はあまりにも謎に満ちた悲劇的なものであったことをご存知でしょうか。
実は、2025年大河ドラマ『べらぼう』でも重要な登場人物として描かれており、その衝撃的な最期は大きな話題を呼んでいます。
天才が迎えた悲劇の真相とは?
江戸時代の天才マーケター、平賀源内の大戦略
夏のうなぎは、実は旬ではありません。
そのため、江戸時代のうなぎ屋は、夏場の売上不振に頭を悩ませていました。
そんなある日、一軒のうなぎ屋が、藁にもすがる思いで相談を持ちかけた相手が、当時、多彩な知識で知られていた平賀源内でした。
「夏にうなぎが売れないのです。何か良い知恵はないでしょうか」
この相談こそが、日本の食文化を変える、歴史的な転換点となったのです。
「本日、土用の丑の日」という名キャッチコピーの誕生秘話
うなぎ屋の悩みを聞いた平賀源内は、こう助言したと言われています。
「『本日、土用の丑の日』と書いた看板を、店の前に掲げなさい」
当時、「土用の丑の日」という言葉は、今ほど一般的ではありませんでした。そのため、通行人たちは「なんだろう?」と、その不思議な看板に足を止めます。
そして、店主が「夏バテには、うなぎが良いですよ」と声をかける。この、平賀源内が考案したシンプルな宣伝文句が、江戸の人々の心を掴み、店はたちまち大繁盛。
その評判を聞きつけた他のうなぎ屋も、こぞって真似をするようになり、やがて「土用の丑の日には、うなぎ」という習慣が、日本中に広まっていったのです。
実は「う」がつく食べ物なら何でも良かった?
平賀源内の戦略が、これほどまでに成功したのには、もう一つの理由があります。
実は、古くから日本では、「丑の日」に「う」のつく食べ物を食べると、夏バテしないという言い伝えがありました。
梅干し(うめぼし)、瓜(うり)、うどん(うどん)…
栄養価が高く、夏バテ防止に効果的なうなぎも、この「う」のつく食べ物の一つ。平賀源内は、この古くからの風習に、うなぎを巧みに結びつけたのです。
天才的なキャッチコピーと、古くからの風習の融合。これこそが、平賀源内の仕掛けた、壮大なマーケティング戦略の正体でした。
そもそも「土用の丑の日」とは?2025年はいつ?
平賀源内の逸話を知ると、次に気になるのが「そもそも、土用の丑の日って、どういう意味なの?」ということですよね。
ここでは、その言葉の本当の意味と、2025年の該当日を、分かりやすく解説します。
2025年の土用の丑の日はこの日!(夏・秋・冬・春の一覧表)
まず、2025年の「土用の丑の日」は、いつなのでしょうか。
実は、「土用の丑の日」は夏だけでなく、年に何回か訪れます。2025年は、なんと7回もあります。
| 季節 | 土用の丑の日 |
|---|---|
| 冬→春 | 1月20日(月)、2月1日(土) |
| 春→夏 | 4月26日(土) |
| 夏→秋 | 7月19日(土)【一の丑】、7月31日(木)【二の丑】 |
| 秋→冬 | 10月23日(木)、11月4日(火) |
この中でも、私たちがうなぎを食べる習慣があるのは、特に夏の土用の丑の日ですね。2025年は、7月19日と7月31日の2回です。
意外と知らない「土用」と「丑の日」の本当の意味をわかりやすく解説
では、この「土用」と「丑の日」とは、一体何なのでしょうか。
- 「土用」とは、季節の変わり目の期間のこと
昔の暦では、立春・立夏・立秋・立冬の直前の、約18日間を「土用」と呼びました。つまり、「土用」とは、次の季節への準備期間のようなものです。 - 「丑の日」とは、十二支の丑にあたる日のこと
ご存知の通り、昔は「子・丑・寅・卯…」という十二支を、年だけでなく、日にも割り当てていました。そのため、12日に一度、「丑の日」がやってきます。
つまり、「土用の丑の日」とは、「季節の変わり目の約18日間の中にやってくる、丑の日」という意味なのです。
土用の期間は約18日間あるため、年によっては、今回のように「丑の日」が2回やってくることもあります。これを、それぞれ「一の丑」「二の丑」と呼びます。
うなぎ以外には何を食べる?現代の「土用の丑の日」の新しい選択肢
「土用の丑の日といえば、うなぎ!」…と、わかってはいるものの、近年、その価格は驚くほど高くなっていますよね。
ここでは、なぜうなぎが高級品になったのか、その理由と、私たちの食卓を救う、最新の「代替品」事情をご紹介します。
なぜうなぎは高級品に?価格高騰の背景にある資源問題
うなぎの価格が高騰している最大の理由は、その資源が世界的に減少しているからです。
ニホンウナギは、絶滅危惧種に指定されており、稚魚の捕獲量も年々減少。完全な養殖技術もまだ確立されていないため、需要に対して供給が全く追いついていないのが現状です。
気候変動や、かつての乱獲などが、その大きな原因と言われています。
スーパーで人気!驚きの「代替うなぎ」最新レポート
そんな中、私たちの食卓の救世主として登場したのが、各食品メーカーが開発した「うなぎ風食品」です。魚のすり身などを使い、見た目、食感、そして味まで、本物に近づけるための、驚くべき企業努力が詰まっています。
- カネテツデリカフーズ『ほぼうなぎ』
白身魚のすり身を使い、皮の質感から身の柔らかさまで、リアルさを追求した一品。SNSでも「本当にうなぎみたい!」と度々話題になります。 - スギヨ『うな蒲ちゃん』
かまぼこメーカーならではの技術で、焦げ目の香ばしさや皮の風味まで再現。魚の切り身に近い食感が特徴です。 - 一正蒲鉾『うな次郎』
ふっくらと柔らかな食感と、少し甘めのタレが特徴。お子さんやご年配の方にも食べやすいと評判です。
さらに最近では、日清食品が植物性素材だけで作った「プラントベースうなぎ」を開発するなど、代替品の進化は、とどまることを知りません。
伝統に学ぶ「う」のつく食べ物で、夏バテ防止!
そもそも、土用の丑の日には、うなぎ以外にも「う」のつく食べ物を食べることで、夏バテを防ぐという、古くからの知恵があります。
- 梅干し(うめぼし): クエン酸が疲労回復を助けます。
- うどん: 消化が良く、食欲がない時でも食べやすいです。
- 瓜(うり): きゅうりやスイカなど、水分が豊富で体を冷やしてくれます。
- 牛肉(うし): スタミナをつけるのに最適です。
高価なうなぎにこだわらなくても、これらの食材を上手に取り入れることで、伝統に根ざした、賢い夏の過ごし方ができるのです。
【豆知識】土用の丑の日に「してはいけないこと」とは?
「土用の丑の日」には、うなぎを食べる以外にも、古くからのユニークな風習や、ちょっぴり怖い「禁忌(してはいけないこと)」があるのをご存知でしたか?
ここでは、知っていると少し暮らしが豊かになるかもしれない、そんな豆知識をご紹介します。
「土いじり」や「新しいこと」は避けるべき?その理由とは
昔から、土用の期間中は、「土いじり」をしてはいけない、と言われています。
これは、この期間、土を司る神様である「土公神(どこうしん)」が、土の中で休んでいると考えられていたためです。
草むしりやガーデニング、家の基礎工事などは、神様の安眠を妨げてしまうため、避けるべきだとされてきました。
これは、季節の変わり目である土用の期間は、体調を崩しやすい時期でもあるため、「無理をせず、静かに過ごしなさい」という、昔の人の知恵が込められているのです。
もちろん、現代の生活で完全に守るのは難しいですが、こんな風習があったことを知っておくだけでも、面白いですよね。
薬草風呂にきゅうり祈祷?ユニークな夏の風習
うなぎ以外にも、この時期ならではの、ユニークな風習が各地に残っています。
- 丑湯(うしゆ):
江戸時代から続く習慣で、桃の葉やヨモギといった薬草を入れたお風呂に入ること。夏の暑さで疲れた体を癒す、まさに日本の伝統的なアロマバスです。 - きゅうり加持(きゅうりふうじ):
主に関西地方のお寺で行われる行事で、自分の名前などを書いたきゅうりに、病気や災いを封じ込め、土に埋めてもらうというユニークな祈祷です。
うなぎだけでなく、こうした様々な知恵を凝らして、日本の人々は厳しい夏を乗り越えてきたのですね。
まとめ:平賀源内から始まった、日本の夏の食文化を楽しもう
この記事では、「土用の丑の日」になぜうなぎを食べるのか?
その最大の疑問にお答えするため、由来となった平賀源内の知られざる物語から、現代のうなぎ以外の新しい楽しみ方まで、そのすべてを解説してきました。
私たちが当たり前のように楽しんでいる夏の習慣。
実は、江戸時代の天才マーケターが仕掛けた、壮大なブランディング戦略だったとは、驚きですよね。
この記事で解説したポイントを、最後におさらいしておきましょう。
- うなぎを食べる由来は、平賀源内がうなぎ屋のために考案した「本日、土用の丑の日」というキャッチコピーがきっかけ。
- 「土用の丑の日」とは、「季節の変わり目の期間(土用)にやってくる、丑の日」という意味。
- 近年は、うなぎの価格高騰もあり、「うなぎの代替品」や、梅干し・うどんといった「う」のつく食べ物で楽しむ人も増えている。
- 土用期間中は、「土いじり」や「新しいこと」を避けるべき、という古くからの風習もある。
高価なうなぎを食べるだけが、「土用の丑の日」の過ごし方ではありません。
その歴史や背景にある物語を知ることで、スーパーで代替品を探すのも、うどんを食べるのも、きっといつもより少し、楽しくなるはずです。
あわせて読みたい